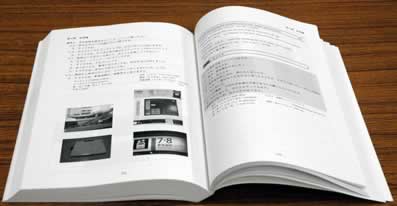聴く・話す・読む・書くの四技能の学習を目指しています。四技能がすべて要求されるような対面授業と頻繁な宿題を通じて、学生は日本語力を総合的に高めていきます。また、常用漢字2,136文字の学習や会話・待遇表現の練習などをICTを活用して自律的に行える環境を整えており、これを少人数制の授業と併用することで高い教育効果を期しています。Googleクラスルームをはじめとした各種オンラインサービスを活用し、デジタル教材の導入と学習・教務の効率化も進めています。
カリキュラム・シラバス一覧
「プロジェクトワーク」「グループ学習」などの選択肢からいずれか一つを選びます。

- プロジェクトワーク(Project Work)
- 学生各自が専門に関連するテーマを決め、文献による調査・研究、アンケート調査、あるいはインタビュー調査などを行います(グループでの研究も可)。日本研究センターで学んだ日本語を実際の場面で活用することで、学習事項の定着をはかるものです。プロジェクトは学生主導で進められますが、講師は週に一時間、学生個人(あるいはグループ)ごとに相談の時間を設け、プロジェクトの進行状況をチェックしながらアドバイスを与えます。
- グループ学習
- 特定の日本語課題に対して関心を同じくする者が、数名でグループを構成し学習します。